�ޗǎ���̍��m�E�s��ɂ�蔭�����ꂽ�Ɠ`���ΐ쌧����s�̎R������́A�����m�Ԃ��͂��ߑ����̕��l�n�q���K��A�R�������u�R���߁v�����₩�Ȍ|�W�O�ł��m����`���ƕ����̑��Â�����n�B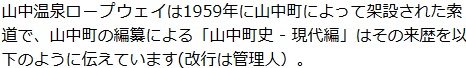 |
|||||
|
|
|||||
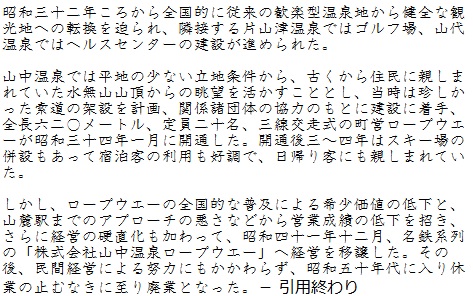 |
|||||
|
|
|||||
| ���p���������������悤�ɁA����܂Łu��l�̉���X�v�ł��������R������́A�������Ƃ̊J�n�ƂƂ��ɁA�A�E�g�h�A�X�|�[�c�ł���X�L�[�ɒ��ځB �C���[�W�]���̊��҂����߂Đ����R�̎R���ɃX�L�[������݂��܂����B���̔w�i�ɂ͏��a30�N��̑�X�L�[�u�[��������悤�Ɋ����܂��B �Ⴆ�A�X�L�[���T�o�[����t�g���̂������������Ƃ����敪���̂��̂ł���悤�ɁA�����ƃX�L�[�͕\����̂̊W��ۂ��Ȃ��甭�W�𐋂��Ă��܂����B �����I�ȃX�L�[�l���̑����������炵���A���a�������畽���o�u�����̑�O���X�L�[�u�[���ȑO���A�����ł�2�x�̑傫�ȃX�L�[�u�[��������܂����B�ЂƂ͐�O�̏��a�����A�����Ă����ЂƂ��R������ɃX�L�[�ꂪ�J�Ƃ������a30�N��ł��B |
|||||
|
|||||
��O�̑�ꎟ�u�[���̍��̃X�L�[�́A���W���[�F���X�|�[�c�F���Z���A����̒n��������ăX�L�[��̐������Ȃ��������߁A�R�X�L�[�̔䗦�����������悤�ł����A���̎��ォ��Q�����f�X�L�[���嗬�ɂȂ�S���e�n�Ŏ��X�ƃX�L�[��J�����n�܂�܂��B �����R�X�L�[��͔�r�I���������ɊJ�Ƃ������߁A�J�ƌ㐔�N�Ԃ͏����ɗ��p�q���K�ꂽ�����ł��B �܂��A�R���ɂ͏��K�͂Ȃ���ϗ��ԁE�V���d�ԂȂǂ̗V���������V���n�i�����R�R���V���n�j��A�W�]��E���X�g�����Ȃǂ̎{�݂�����A���a30�N��͂��Ȃ�̓��킢���݂��Ă����悤�ł��B�i�_�C�]�E����̃T�C�g���S�����̐����R�V���n�̋M�d�Ȏʐ^�����邱�Ƃ��o���܂��B�j �������A���a40�N��ɓ��鍠����A�ߍx�ɂ���ݔ��̏[���������q�ፂ���X�L�[����A1970�N�i���a45�N�j�ȍ~�ɔ��R�[�ɑ������ŃI�[�v�������X�L�[��Q����1�ɗ��p�q������A1978�N�i���a53�N�j10���A���ɍ������^�x�A�X�L�[����x�Ƃɓ���܂��B����̃p���t���b�g�̎ʐ^�͍����A�X�L�[��Ƃ��ɖ����ɋ߂����a50�N���̂��̂ł��B �₪��1981�N�i���a56�N�j4���ɖ��S�A�R�����A�R�����ً����g���̏o����Ђł��銔����� |
|||||
�y�K��L�z�@2007�N12�� ���݁A�����R�ɂ������w�ɂ͎R���E�R�[�Ƃ����S�ɓP������Ă��܂����A�R���ɂ͉w�ɂƘA�����Ă����W�]�䂪���̂܂c����Ă��܂��B�����ɓW�]��Ƃ��Ă͔����ɋ@�\���Ă���Ƃ����������ł����A��͂��\�ƌĂ����ӂ��킵���Ȃ܂��ł��i�ʐ^�@�j�B �W�]��̎ʐ^�Ƀ}�E�X���悹��ƁA�R���w�Ƃ̘A�������̎ʐ^�ɕς��܂��B�w�ɂ��������ʐ^�������͐[���M�ŁA��\�͉�������܂���ł����B �R���V���n���������ꏊ�ɂ͗V��{�݊֘A�ƍl������R���N�����X�ɂ���A�M�̒��ɗV���d�Ԃ̃g���l���炵����\���c���Ă��܂����i�ʐ^�A�j�B �R�[�w�̖��c�Ƃ��āA�㉤�����̖�t���̘e�ɎR�[�w�ɂւ̃A�v���[�`�������ƍl������K�i���c���Ă��܂��i�ʐ^�B�j�B �K�i����肫�������͍s���~�܂�̏����ȃX�y�[�X�ɂȂ��Ă��āA�����ɂ͐ԎK�т��Ɩ����Ɛ����ݏ�i�����H�j�̈�\���c���Ă��܂����i�ʐ^�C�j�B �R�[�w��2�̌����i�������E�S���h���������j�ō\������Ă����悤�ŁA�����͔������̌������������ꏊ�̂悤�ł� |
�ʐ^�@ �ʐ^�A �ʐ^�B �ʐ^�C �ʐ^�̍��������������������Ɛ��肳���ꏊ�B�i�}�E�X���悹��ƈ�\�̎ʐ^�ɁB�j |
||||
| �Ȃ��A�R���̖k���ɂ������Q�����f�́A���H��{�����c���Đ[���M�Ɗ��i�A�т��ꂽ�l�q�j�ɕ����Ă��āA�������Ƃ������t�g�i�����R�X�L�[���t�g�F1958�N�ː݁j�̈ʒu�����R�Ƃ��܂���B�����Ƃ���R�[�X��300m�ɂ������Ȃ������ȃQ�����f�������悤�ŁA�����Ă݂������ł͌X��10�`20�����炢�̏����������Q�����f�������Ǝv���܂��B ����̖K��ł͍ŏ��A�R�[�w�ɂ̈ʒu�����炸�A�㉤���̎�����E���E�����Ă���ƁA���傤�Njߏ��̕������ԏ�ɎԂ����Ă���Ƃ���ɑ��������̂Őq�˂Ă݂�ƁA�u���̉w�ւ́A����t����i�n���̐l�͈㉤���������Ăԁj�̊K�i����^�������s���ď����~�肽�Ƃ��납��o�������B�v�Ƌ����Ă���܂����B �������q�ɏ���Ď��Q�����Â��n�}��ʐ^�i�j�̃R�s�[�Ȃǂ����o���ă��[�v�E�F�C��X�L�[��̂��Ƃɂ��Đq�˂�ƁA���̕��͐e�ɋ����Ă���A�Ō�Ɂu�Ȃ������Ԃ�ς�����������Ƃ�悤��ˁB�v�ƌ����ď��Ă��܂����B ���́u�ւ�Ă��߂��鎿��v��n���̐l�ɂ��鎞����Ԓp���������ł��G |
|||||
|
|
|||||
����1 ���z��������X�L�[��(1970�N�J�Ɓj�E���R����X�L�[��i1971�N�J�Ɓj�E���R�ꗢ��X�L�[��i1977�N�J�Ɓj |